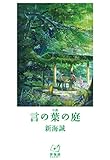5月に読んだ本からおすすめ10冊を紹介。
5月に読み終えた本は31冊。
その中からおすすめの10冊を紹介!
第10位
『饗宴』
プラトンによる一冊。
おっさんたちが集って「美って何なのよ?」と語り合う与太話。
そこには論駁大好きおじさんであるソクラテスも参戦して、さあどうなる!!?
なんて内容の一冊。
そして最後のオチがなかなか秀逸で、「伏線がそこに!!?」なんて後々に(メタ的な意味でも)もわかってくる演出。
ちょっとネタばれしてしまえば「作者がどうしてプラトンなの?」と言ったような疑問に対する答えを示すような。
第9位

- 作者: オスカーワイルド,Oscar Wilde,西村孝次
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1953/04/10
- メディア: 文庫
- 購入: 3人 クリック: 16回
- この商品を含むブログ (21件) を見る
オスカー・ワイルドによる戯曲を3篇も収録した一冊!
そんな中でも個人的には『ウィンダミア卿夫人の扇』と『まじめが肝心』が特に面白く感じ、今に読んでも古臭さを感じさせぬエンターテイメント感!
今の時代的に言えば、三谷幸喜やアンジャッシュのような作品らしさ。
そのような風体を感じるような内容であって、コメディとしても完成度高い。
そして残りの一篇『サロメ』は一読して受けた印象”メンヘラ!”
ヤンデレ要素も濃厚で、原初的。
なので昨今のツンデレ・ヤンデレという、ヤン坊マー坊みたいな二大頭の概念は、この時代から存在していたのか!と驚愕。
あとは全体的に富むユーモラスな会話等々も印象的で、
「悪い女は人を困らせるし、善い女は周りをうんざりさせる」
なんて台詞は特徴的。
第8位

- 作者: フレッドチャペル,Fred Chappell,尾之上浩司
- 出版社/メーカー: 東京創元社
- 発売日: 2000/08
- メディア: 文庫
- 購入: 2人 クリック: 62回
- この商品を含むブログ (15件) を見る
表紙から既に歪な雰囲気を表出させる本書は、そのインパクトに負けず劣らず内容はなかなか突飛で壮大かつ驚愕的。
なかでも「こんな終わり方ってあり!?」なんてつい思ってしまうような小説こそ稀有で、こんな風に驚いたのは本当に久々。
そして本書の文庫としては、解説が実に秀逸かつ重要で、これによってようやく「ああ、そういうこと」と腑に落ち、解説なしでは成立していないようにさえ思える一冊。
すると思いがけず勉強にもなる内容で、それは一種の物語論として。
昨今読んだ小説の中では、そのイマジナリーさはSFでもないくせにすさまじく、
文学としての別次元の可能性を感じさせてくれる珍しい作品。
ゆえに、妙にお勧め。
第7位
『戸塚教授の「科学入門」 E=mc2 は美しい!』
自伝的側面もありながら、ポピュラーサイエンス書としても十二分に啓蒙的な内容で、価値があるよう思えた一冊。
個人的にハッとしたのは植物に関して、大木が上部にまで水分を運ぶ仕組みについてであり、それまでは「毛細血管的な作用かな」と思っていた。
だが本書曰く「水分子の放出(蒸発)による剥離によって、その部分に下の水分子が吸い付くように引き付けられるため」とのことで、実にわかり易い!
ほかにも「光の科学」についての章では、物理の発展において光に関する科学が如何に重要であったか?それに伴い光学の発展を数式も用いて具体的に解説!
読み応えたっぷりで、たとえば振動数の観測地の誤差が「どうして!?」となった話などもあり、その解決までの流れも具体的。
物理はミステリーに似ている、なんて言葉を聞いたことがあるけれど、現象の犯人探しとは犯人を突き止めるが如く好奇心を刺激する!
なので「なーるほど、実際の分子はいろいろな運動エネルギーを持って振動するのか。ということはつまり…」と著者と一緒になぞ解き楽しめる!
また素粒子に関する解説では専門だけあってとても平易な言葉で内容の本質を示してくれており、各用語の理解は捗りやすい。
それこそ、無駄のない言葉のチョイスこそ最適で、さすが最小単位を取り扱かおうという専門家!なんて思ってしまったり。
楽しく読めて、とても勉強にもなるのでお勧めの一冊。
第6位
『小説 言の葉の庭』
餅は餅屋というけれど、餅屋であった。
そんな、まるで「深淵をのぞく時、深淵をのぞいているのだ」なんていう面白い言葉みたいなのをつい思い出して混乱をきたすはめになりそうにならない一冊。
要は「新海誠」といえば、『君の名は』が特に有名な映画監督であり、文筆業とは専門にあらず。
そんな風に思い込んでいたのだけど、実際に読んでみればあら不思議。
なんとも見事な達筆具合。
自然の描写は枝葉に光が差して感じ、都会の情景、たとえる蜂の巣は写実的。
人の情緒の描き方も上質であってリアリズム的に「人間がちゃんと描けている」というよりかは「言葉に人が舞っている」と感じるほどにはダイナミクス!
さらに彩り豊かな登場人物の個性こそわかりやすく「監督は人の心を着色して見ているの?」なんて聞きたくなるほどには個々人の性格や内省をしっかり区分けできている。
あと思うのは、これほど文章として巧妙に表現できるからこそ、あのような美しい映像として表わせるのであり、頭の中のイメージを上手く、そのままにも転化しているのでは!?という風にも感じた。
とかく本書は傑作小説であるとは思う。
第5位
『ことばの獲得 (ことばと心の発達)』
ことばの獲得について。
関連した論文7つが載せられた一冊。
どの論文もなかなか面白くて、特に印象的なのは「形式言語」についての一幕。
時間があれば後にもう少し、詳しくまとめる予定に。
第4位
『道徳性の発達と教育―コールバーグ理論の展開』
道徳とは。
正直、期待していた内容とは少し違っていた。
というのも、本書では「道徳」それ自体の存在について追究するものかと思いきや、その定義性については踏み込まず。
あくまで「道徳」それ自体は絶対的に存在しているとの過程から、その派生と派生具合についてを研究、検討する内容であったため。
それでもなるほど、一読する価値は十分にあったと思わせる内容ではあり、道徳性とその発達について独自の理論を展開しつつ、その解説と結果を示すもの。
時間があれば後日、もう少し詳しくまとめようかと。
第3位
『アメリカの鱒釣り』

- 作者: リチャードブローティガン,Richard Brautigan,藤本和子
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 2005/07/28
- メディア: 文庫
- 購入: 6人 クリック: 45回
- この商品を含むブログ (137件) を見る
読む麻薬。
なんて表現こそ適切に思える小説?エッセイ的ともとれる作品で、といっても麻薬を嗜んだことはもちろんないのであくまでイメージとして。
なのでより現実的な物言いで例えれば、酒をがばがば飲んで訪れるまどろみ感覚のような、酩酊して世界が歪曲しながらも、なんだか妙な気持ちよさを味わっているような感覚に陥るような不可思議作文。
しかし本書が当時のアメリカにおいてよく売れた、なんていう事実も妙に納得。
できる内容であり、薬物を染み込ませたような文章こそまさに特筆的。
よくよく聞く「その話って深いね」みたいな話はおおよそが「いやいや、それは聞き手の底が浅いから、何でも深く感じるんだろ」なんて思えながらも、本書においてはまさに例外。味わい深さという点においては特殊で、各々の器に流し込むその話の成分は器を溶かすが如く。まあ一言で言って、へんな小説へんな本。
第2位
『ウォール街の物理学者』
「星の動きは計算できるが、(相場を動かす)人の狂気は計算不能だ」
こんな言葉を残したニュートン。
この言葉こそ、ある意味において本書の内容を如実に表しているように思えたり。
そうした本書は題名が示すとおり。
経済界に物理学者が参入とした。
と、ただそれだけのことであり、それだけのことがもたらした衝撃を描くノンフィクション。
「理論が論理どおりに従うか」
そんな、物理的法則を経済学に当てはめ試行錯誤の学者たちの物語。
一時期まで埋もれていた、偉大な数学の定理などにも(それが経済学と多大な関係があったため)スポットを当てたり、先人の頭の良さ(金融として、一般的な人の好ましい状態に導く、という意味において)に触れるにはうってつけの内容。
そしてもちろん、とうぜんのようにカオスやフラクタルについても言及し経済学への応用の解説も。
そして意外な小ネタ、トリビアも多くてそれが面白く、マンデブロなどは”幾何に優れた才能を”なんていうのはフラクタルから容易に想像できようとも、勉学においては戦争の影響が色濃かったこと、また注目すべきは
「いかなる数学的な問題も幾何的な”見える形”として変換して捕らえる才能に特化していた」という事実がありながらも「掛け算が苦手」なんていう意外さも。
バシェリエの「ランダムウォーク」なんて早々から飛び出し、オズボーンによる「対数正規分布」はともかくソープによる「デルタヘッジ」などは近年の経済においても親密に関係しているので近代の経済学と数学との関連を知る上でも便利であるし、ブラックにおける「オプション価格理論」も同様。
あとはギャンブルへの応用をしようと試みた輩もいるので、そこでの挑戦とその結果などはエンタメ性もあって楽しめる。
普通に読んでも十分に面白いが、「理論」と「論理」の違いをよりよく理解してから読めばより楽しめる一冊。
おすすめ。
第1位
『人類の知的遺産〈73〉ウィトゲンシュタイン』
紙に書かれた過去は、先人の足跡に過ぎない。
先人が何を見たかは、辿らなければわからない。
上の言葉はモンテスキューが残した指摘で、なるほど尤もだなと妙に納得。
というのも人が言わんとする言葉には少なからず行間が含まれるもので、
その行間を読むためには相手のことを知ることが必須。
そして逆説的にいってしまえば、相手のことを知り尚且つその上で言葉を吟味する必要があるからで、これを一言でいってしまえば「認知バイアスを打ち破るため」。
ものすごく簡単にたとえれば「偉い学者さんが言っているのだから、絶対なんだ!」なんていう、こうした安直な思い込みを見直すためであり、同時に、人を知って実際のその人の思想が偉大かどうかを己で判断することができることに大きな効果があると言える。
よって、哲学なんかは特にそうした面*1が顕著に重要で(すると、この文章自体がその対象にもなるようであって、不完全性定理みたいなぐらぐらする基盤の不安定さを感じさせるかもしれないけれど)、その思想を知る上で
「はて?そもそもこの人はでは、どうしてそのような事を思うに至ったのか?」
を疑問に思い探るのは、彼の語る言葉を言葉以外からも理解する鍵となる。
何故なら、彼の思想は思想それ自体として思惟、つまり思うことで存在するのであり思う時点においては外に出ていないのだから。
よって、それを現象化、表象化として言語化する時分には、そこに含まれる情報とは必ずしも抽象化時とイコールではなく、状態の変化によってそぎ落とされる情報が、言語以外として含まれる。
そこを救い上げる手段としての共有こそが、相手を知ることであり、非言語的思想という抽象的な削がれた情報を選り得るひとつの方法なのだから。
そんな状態において、うってつけな本書としてはウィトゲンシュタインの生涯についてをまず綴り、生い立ちや家族構成、生まれ育った背景など彼の人生観をその人生を通して思い描く。同時にウィトゲンシュタインその人の思想についても解説。
すると見えてくるのはまさに、彼の雄弁多大なメタ的にも読める複合的かつ逆説的な言語の捉え方。
それこそ、前期におけるノンバーバル・コミュニケーションへの軽視など、数多の立場をとって読めば構成自体がなるほど、こっけいでありそして同時に鳥瞰的な示唆があるのだと。
言ってしまえば、行間の行間を読めと訴えるような、隙間の存在を示す。
こうした言語への理解はまさに、着ぐるみをまとった言語をはがすようでもありめその正体を解き明かそうとするような異臭さ漂う行為かもしれない。
けれどそれは、次元を一つ増やして言語の内容を理解するという試みでもあって、
熟読すれば思考の進化を感じられる一冊。
おすすめはしないけど、おすすめ。
*1:答えが確実でないゆえに